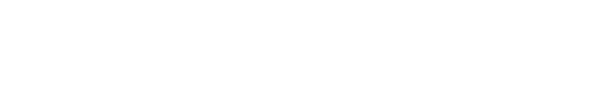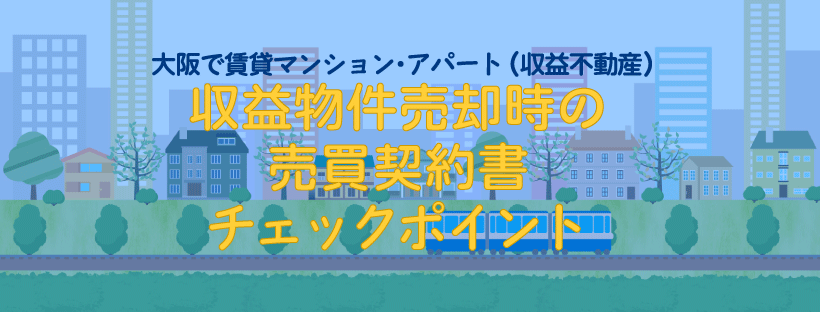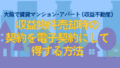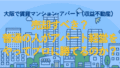一棟賃貸マンション・アパートなどの収益物件を売却するとき、仲介会社が売買契約書を作成してくれると思います。この契約書、事前にきちんと内容を確認しているでしょうか?
仲介会社の多くは、買主のお客様には細かく説明しますが、売主にはあまり詳しく説明しない傾向があります。
しかし、事前に契約書のドラフトはメールでもらえる事が多いと思います。その内容を、一つ一つ確認してほしいと思います。
知らない間に売主にとって不利な内容になっていたり、後々トラブルになりかねない内容になってることも少なくないのです。
ここでは、その中でも特に重要な部分について解説しました。
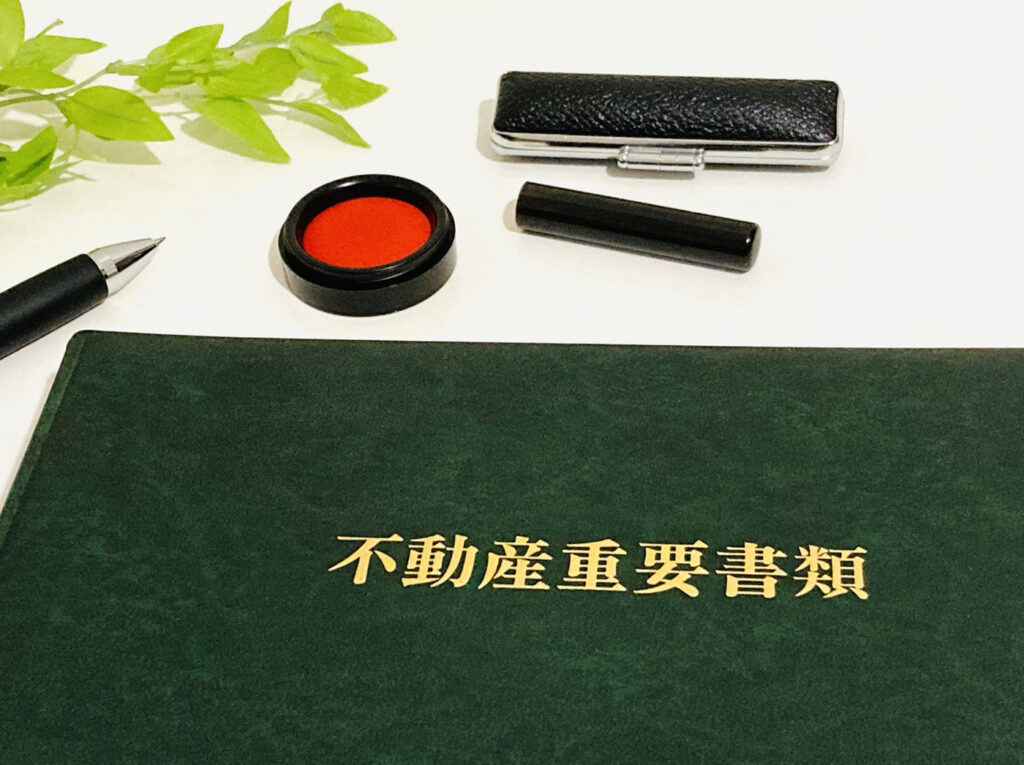

土地と建物の按分をどうするのか?
固定資産税評価額で按分
土地と建物の按分をどうするかは不動産取引において、よくもめる箇所です。
なぜなら、売主と買主の利害関係が対立する箇所だからです。
売主は、建物比率を少なくするほうが有利です。
なぜなら不動産取引において、土地には消費税がかかりませんが、建物には消費税がかかるからです。建物比率が高いとその分、消費税の額も増えますので、消費税課税事業者の場合は、建物比率を少なくしたほうが税額が少なくなります。
反対に買主は、建物比率が高いほど有利になります。
建物は減価償却が出来ますが、土地は減価償却が出来ません。そのため、建物比率が高いほど節税効果は高くなります。
この全く相反する立場を調整するために、通常は「固定資産税評価額」で土地と建物を按分します。
毎年、市役所から固定資産税の納付通知書が届くと思います。これに、土地と建物の評価額が記載されています。この金額に応じて按分するのが、売主買主両方に公平な按分法と言われています。
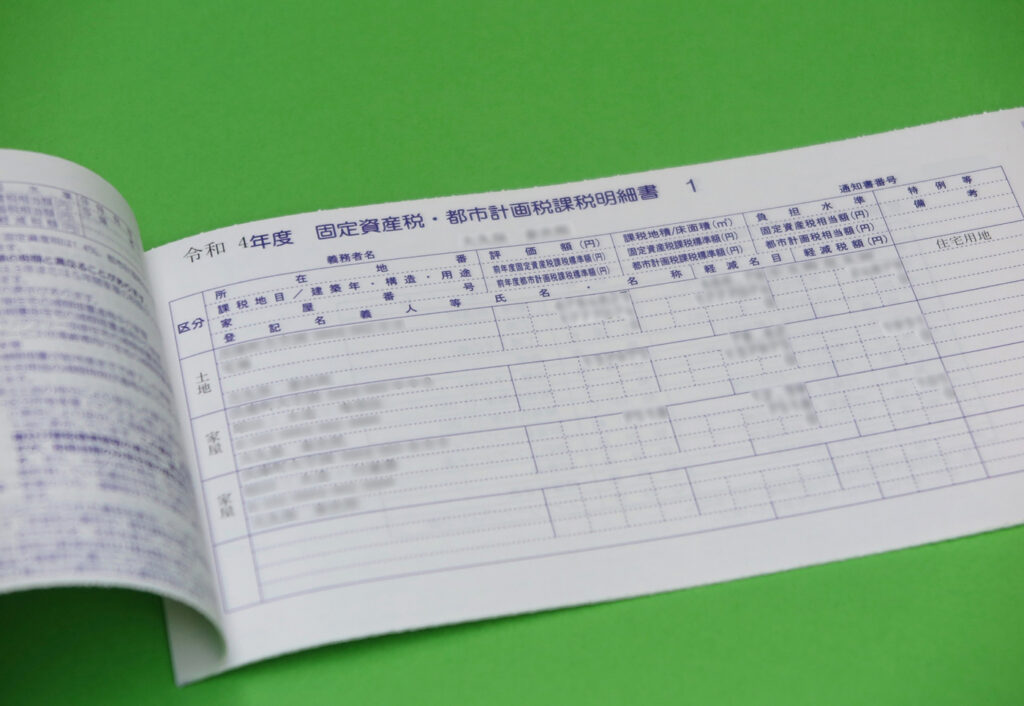
確認不足で消費税を多く払う羽目に
大阪市港区のN社は大阪市大正区に保有していた一棟賃貸マンションを売却しました。売却後に税理士に契約書を見せたら、消費税の額が多いのではないかという指摘を受けました。計算してみると建物の割合が多く、本来払うべき消費税の額よりかなり多くなることが分かりました。引き渡しまで終わってしまったので、今更変更する事はできませんでした。
売買契約書のドラフトが届いたら、この按分に応じて土地と建物の価格が決められているのか確認するようにしてください。ここは意外と多くの人が見落とすポイントなのです。
境界を明示するのか非明示で取引を行うのか
境界はトラブル要因のひとつ
境界の問題は、不動産取引における最大のトラブル要因の一つです。境界が不明瞭なまま取引を行うと、あとからもめることが多く、場合によっては裁判にまで発展することもあります。そのため、契約前に土地家屋調査士に依頼して、筆界確定を行う事が望ましいです。
もちろん、以前に筆界確認を行っており、その書類が残っている場合は新たに行う必要はありません。
問題は、筆界確認を行わないで取引をする場合です。収益不動産の取引の場合、測量や筆界確認を行わないで取引をすることも多いです。その時に、何も書かずに取引を行えば、あとからトラブルに発展することも少なくありません。買主から了解をもらった上で、境界を明示せずに取引を行う旨を契約書に盛り込む必要があります。

境界トラブルを回避する例文
例えば、次のような一文を入れておくのが良いでしょう。
——————–
本件は、公簿面積による取引とし、現地立会い、敷地面積の実測、及び境界標の設置はあらたには行いません。引渡し後、隣地所有者等との間で境界について疑義や紛争が生じたとしても売主は一切の責任を追わず、買主の責任と負担において処理・解決するものとします。
———————–

現状有姿の契約である旨の明記
知っていることはすべて伝える
「現状有姿」での契約は、収益物件を売却する際によく用いられる条項ですが、単に一言入れるだけでは不十分なケースが多いです。特に中古物件では、設計図書の内容と実際の状態が完全に一致するかどうか、登記されている面積と実際の面積が一致するかなどは誰にも分かりません。
これに対して、売主が全責任を負うのは酷でしょう。
そのため、書面などで残っているデータと実際の状態と違っている部分はどこなのかを出来る限り詳細に買主に伝え、それを契約書に盛り込む必要があります。知っているのに伝えないと、契約書に「現状有姿」と書いていても売主の責任を追求されることも少なくありません。
現状有姿トラブルを回避する例文
そのため出来る限り告知を行った上で次のような一文を盛り込むのが良いでしょう。
———————
対象不動産建物の現状における種類、構造、意匠等は、対象不動産建物の全部事項証明書、確認通知書、もしくは竣工図等の各記載内容と異なる可能性がありますが、本契約では対象不動産建物の現状における種類、構造、意匠等を優先するものとします。
——————-

契約不適合責任免責の落とし穴
不具合はすべて契約書に盛り込む
契約不適合責任は以前は「瑕疵担保責任」とよばれていましたが、民法の改正で現在の言い方になりました。
収益物件を売却する際、売主が宅建業者である場合を除き、契約書には契約不適合責任は免責という内容の記載をすることが多いです。売主としては売却後のトラブルが一番嫌なものですので、そうならないように対策をする必要があります。
しかし、こちらも契約書に「契約不適合責任免責」と書いてあれば良いという簡単な話ではありません。売主が把握している不具合は全て告知したうえで、どうしても知り得なかった不具合のみ責任が免責されるというのが、契約不適合責任免責の考え方と理解していただければと思います。売却時に売主が把握している不具合は、契約書や重要事項説明書に全て盛り込むようにしてください。この作業を怠ると、後々トラブルになっても免責にならない事も多いです。
入居者の一言から発覚
奈良県奈良市にお住いのKさんは、奈良県大和高田市に持っていた一棟賃貸マンションを売却しました。一つの部屋で漏水があるのを知っていましたが、修理をする費用を惜しんでそのまま何もせずに売却をしました。
引き渡し後に、買主は入居者から漏水があることを教えられました。漏水の修繕を要請していたにも関わらず、対応してなかったことが発覚したのです。これは知っていて告知しなかったことなので、契約不適合責任免責にはなりません。
漏水箇所を突き止めるのに手間がかかり、修繕費はかなり高いものになりました。当然、その費用は売主のKさんの負担です。もし自分で修繕を手配していたら、もっと安く修繕できたのにと悔やみましたがあとの祭りでした。

契約不適合責任トラブルを回避する例文
そのうえで、次のような一文を盛り込むのが良いでしょう
———————-
売主は対象不動産の不具合について一切の契約不適合責任を負わず、引渡時の現状有姿にて対象不動産を買主に引渡すものとします。
本物件は築●年を経過しており屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、排水管、ガス管等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化が認められるところであって買主はそれを承認し、それを前提として売買契約書所定の代金で本物件を購入するものとします。
本物件引渡後に自然損耗、経年変化による劣化・腐蝕等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、設備の故障等があったとしても、それらは契約不適合に該当するものではなく買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとします。
——————-
他にも注意するべき点はいくつもありますが、ここで説明したことは最もトラブルが多い箇所です。
必ず確認を行い、売却時のリスクを最小限に抑えることうようにしてください。

収益物件売却時の売買契約書チェックポイント Q&A
Q1. 土地と建物の按分はどのように決めるべきですか?
A1.通常は固定資産税評価額に基づいて按分します。土地には消費税がかかりませんが、建物にはかかるため、按分方法によって税額が大きく変わるためです。
Q2. 按分方法を確認しないとどうなりますか?
A2.建物比率が高く設定されていると、不要に多くの消費税を支払うことになり、損をする場合があります。契約書のドラフトで必ず確認しましょう。
Q3.境界が不明瞭なまま取引をするとどうなりますか?
A3.後に隣地所有者とトラブルになる可能性があります。事前に「非明示」であることを契約書に記載しておくことが重要です。
Q4. 境界トラブルを防ぐにはどうすればいいですか?
A4.境界確認を省略する場合でも、「現地立会いや測量は行わない」「トラブルが生じても売主は責任を負わない」と明記する一文を契約書に加えることで回避できます。
Q5. 「現状有姿」の契約であれば、すべての責任が免除されますか?
A5.いいえ、売主が把握していた不具合を隠していた場合は責任を問われます。知っている情報はすべて告知し、契約書に記載しておくことが必要です。
Q6. 契約不適合責任を免除するにはどうすればよいですか?
A6.事前に把握している不具合をすべて契約書や重要事項説明書に明記したうえで、「引渡後の劣化・損耗は買主が負担する」旨の文言を契約書に盛り込むことが大切です。
Q7. 過去に契約不適合責任でトラブルになった例はありますか?
A7.はい。奈良県の売主が漏水の事実を知りながら告知せずに売却し、買主に指摘されて高額な修繕費を請求された事例があります。隠さずに告知することが重要です。
Q8. 売主にとって最もリスクが高い契約内容はどこですか?
A8.土地建物の按分、境界の明示、現状有姿の内容、契約不適合責任の扱いは特にトラブルが多い箇所です。必ず事前確認し、書面に反映させましょう。